皆さんの中には、就労継続支援B型の就労作業は施設内のみだと思っている方やそのためにサービス(支援)の数や種類が少ないと思っている利用者の方、もっとサービス(支援)の幅を広げ利用者のできることを増やしたい、または拡充したいと考える事業所の方などいることでしょう。就労継続支援B型は、障害や体調に不安のある方が自分のペースで働ける環境を提供する福祉サービスです。その中でも近年注目されているのが、事業所の外に出て地域の企業や施設で作業を行う「施設外就労」という支援形態です。
施設外就労は、利用者にとって実践的なスキルを身につけられる貴重な機会である一方、事業所にとっては、制度理解や契約、支援体制の整備など、導入にあたって多くの準備が求められます。
下記では、施設外就労の基本的な仕組みから、就労継続支援B型作業所での導入手順、実施後の運用・管理方法までを丁寧に解説しています。これから施設外就労を始めようと考えている事業所の方、制度を詳しく知りたい企業の方はぜひ参考にしてください。
本記事を読むことで施設外就労とは何か、またその位置づけなど施設外就労の基本的なことの理解を深め、また疑問をもったことへの解決につなげていければ幸いです。

そもそも施設外就労ってなんなのかな?

就労継続支援B型で施設外就労できるのかな?

取り入れたいけど、方法がわからない。
このような悩み、疑問がある方は必見です。この記事を読むことで施設外就労の基本的知識と、導入方法を知っておくとこれからの就労支援の拡充にもつながります。
- 施設外就労とは?
- 就労継続支援B型での位置付け
- メリットおよびデメリット
- 施設外就労の導入方法
- まとめ
就労継続支援B型作業所の施設外就労とは?

就労継続支援B型は、障害や体調の不安を抱える方が自分のペースで無理なく働ける環境を提供する福祉サービスです。その中で、注目されているのが「施設外就労」という取り組みです。施設外就労とは、簡単に言うと就労継続支援B型作業所の利用者が施設の外に出て、実際の企業や地域の現場で作業を行う形態をさします。
また、就労継続支援B型作業所側からみた施設外就労とは、原則として利用者が事業所に通所して支援を行いますが、事業所が企業から請け負った作業を、利用者がその企業内で行う場合があります。この場合、就労継続支援の事業所の職員が同行して所定の支援を行った場合が施設外就労となります。
施設外就労には、身近な作業で考えると、清掃作業や、農作業などさまざまな生産活動、支援があります。下記では、施設外就労とはなにか、また障害者総合支援法からみた施設外就労の位置づけについて詳しく解説していきます。
施設外就労とは?
就労継続支援B型における「施設外就労」とは、障害や体調面の課題などにより一般就労が難しい方が、福祉事業所の外部にある企業や団体の作業現場で就労体験を行う取り組みです。通常、B型作業所内で行われる軽作業や内職とは異なり、より実践的な作業環境で仕事に取り組むことができるのが特徴です。
施設外就労の主な業務内容には、農作業、清掃、商品の仕分け・梱包、飲食店の補助業務、リネンサービスなど、地域社会や企業との連携を通じて実施されるものが多くあります。これにより、利用者は「働くこと」のリアルな環境に身を置くことができ、社会参加や自立につながっています。
厚生労働省は、「施設外就労は、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結し、当該企業内で行う支援と定義しており、原則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものである。」と述べています。
参考:「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」
分かりやすく説明すると、就労継続支援B型作業所における施設外就労とは、企業などの外部事業者と「この作業を担当してください」という請負契約や業務委託契約を結び、利用者がその企業の職場で作業を行う仕組みであり、原則として施設外就労の作業は、利用者が施設の敷地外にある企業や団体などの実際に活動している場所(実在の現場)で、生産活動や職業訓練などを行いう形態のことを指します。形だけの契約や仮の場所では認められません。
さらに、「就労継続支援事業における施設外就労について(平成24年10月26日 事務連絡)」の中で、以下のようにも記しています。
「就労継続支援B型事業所の利用者が、事業所外の企業・農場・商業施設等において、生産活動を行う形態であり、当該活動は、あくまで当該事業所が主体的に行うサービス提供の一環として取り扱われるべきである」。
では、施設外就労にはどのような業種、作業内容があるのか一般的なものを紹介します。
- 農作業(収穫、除草、農業用ビニールの設営など)
- 清掃業務(公共施設や商業施設の清掃)
- 軽作業(商品の袋詰め、シール貼り、仕分けなど)
- 工場での部品組立・梱包作業
- 飲食業の補助作業(下ごしらえ、洗浄、配膳など)
就労継続支援B型では雇用契約を結ばず作業をするため、時間の短い作業や事業所内の軽作業、内職といった作業が中心となります。そのため作業所内での作業は閉鎖的な環境になりがちです。ですが、閉鎖的で引きこもりがちな環境の打開策として施設外就労があります。施設外就労は施設内から一歩外に出て、「より実社会に近い環境で働く経験」を提供する支援の一環として重要な一面もあり、施設外就労が地域社会への参加や一般就労への第一歩を担っています。
このように多様な業務を通じて、利用者は「作業スキル」「生活リズムの構築」「対人関係」などの能力向上が期待されています。
契約形態について
施設外就労を導入する際、事業所と外部企業との間で「どのような契約を結ぶか」は非常に重要なポイントです。そのため契約の形態は、雇用契約ではなく、業務委託契約または作業委託契約という形が基本となります。これにより、事業所が外部企業から業務を受託し、その業務を利用者が実施するという構図が成立します。
契約の形態によって、作業の責任範囲や報酬、支援体制の内容が明確になり、トラブル防止にもつながります。
たとえば、利用者が直接外部企業との雇用契約を結ぶわけではありません。そのため、作業中の責任や管理はすべてB型事業所が担うことになります。これにより、体調の変動がある利用者でも安心して働けるよう、事業所が随時サポートできる体制が整えることが可能になります。
※請負契約とは、「成果物に対して報酬が支払われる」契約形態です。
特徴
- 完成した成果物(例:部品の組み立て、袋詰め作業など)に対して、事業所が報酬を得る。
- 成果の完成に対して責任を負う。
- 作業工程や支援の方法は、事業所が主体的に決定。
メリット
- 作業の成果が明確で、報酬の計算がしやすい。
- 企業からの過剰な指示を避けやすく、労務提供と誤解されにくい。
留意点
- 完成責任があるため、成果が未達だと報酬に影響することも。
- 作業内容・品質・納期について、契約書で明確に定めておく必要がある。
※業務・作業委託契約とは、「特定の業務の遂行に対して報酬が支払われる」契約形態です。
特徴
- 成果物ではなく、作業そのものの提供に対して報酬が発生。
- 例:清掃業務、農作業、施設管理補助など。
- 請負契約と比べると、完成責任は緩やか。
メリット
- 利用者が日常的な労働体験を積むには適している。
- 成果が出にくい作業や、継続的な業務にも対応しやすい。
留意点
- 業務の指示系統が曖昧だと、「労働者性がある」と判断されるリスクがある。
- 企業側が直接利用者に指示を出すと、労働法上の問題につながる可能性も。
- 業務委託は広範囲的に業務全体や専門的な業務を委託する場合に使われます。
- 作業委託は比較的単純な作業や工程の一部を委託する場合に使われます。
障害者総合支援法に基づく施設外就労の位置づけ

まず障害者総合支援法とは、正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。この法律は障害のある人が地域で自立した生活を送れるよう、必要な福祉サービスを包括的に提供することが目的です。
就労継続支援B型作業所は、障害者総合支援法の「障害福祉サービス」の体系として、生活介護・就労系支援・短期入所などが定められており、この法律の第5条の中の一つにあたります。
また就労継続支援B型作業所は、雇用契約を結ばない形で就労支援を提供する福祉サービスです。身体や知的・精神的障害や難病などにより、一般企業での雇用または就労が困難な方を対象とし、作業訓練や日中活動の場を提供しています。
就労継続支援B型は、施設内での作業を基本としていますが、事業所外での作業(施設外就労)も制度上明確に認められており、就労継続支援B型の支援の「一形態」として取り組むことも可能です。
施設外就労は、障害者総合支援法に基づいて「就労継続支援B型の提供形態の一つ」として、厚生労働省の通達などで運用基準が定められています。
そのため、厚生労働省による明確な位置付けとして、「事業所の外において、当該事業所が雇用・業務委託・請負等により外部の作業現場を確保し、利用者に対して就労の機会を提供する活動であり、あくまで当該事業所が提供する福祉サービスの一環である。」と示しています。
つまり、施設外就労とは「外部(施設外)に出て働く」ことではありますが、法律上はあくまで事業所内の支援活動と同等に扱われる通所支援であるということです。
障害福祉サービス事業の指定基準においても、施設外就労は「個別支援計画に基づく支援の一部であり、支援記録の整備、安全管理体制の確保、スタッフの同行やモニタリングなどが求められる」と明記されており、報酬請求においても、事業所内作業と同等に位置づけられるため「日額単位での報酬請求が可能」となっています。
施設外就労作業中利用者が外部の現場で作業を行う場合でも、管理責任・安全確保・支援内容の記録はすべて事業所の責任で行う必要があり、これらが適切に行われていなければ、支援の質の低下や利用者の安全リスクにもつながります。そのため厚生労働省や自治体も監査等で重視する項目でもあるため注意が必要です。
就労継続支援B型作業所が施設外就労を導入するメリットとデメリットを比較解説!
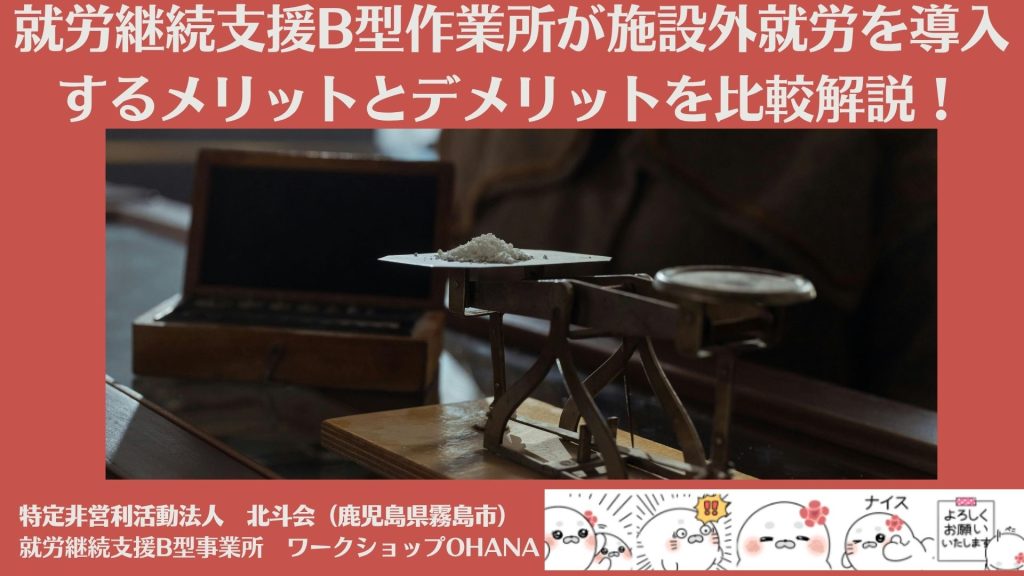
就労継続支援B型作業所では、基本は施設内での軽作業や内職などを中心とした就労支援が行われていますが、近年では、地域企業や農場、公共施設などと連携した「施設外就労」を積極的に導入する作業所も増えています。
閉鎖的になりがちな施設内の作業に対して、施設外就労は、実際の職場環境に近い形で作業に取り組めます。そのことからも考察できるように、利用者の社会参加やスキル向上に大きく貢献するとされてますが、一方で運営面・管理面での負担も伴うので注意が必要となります。
ここでは、就労継続支援B型作業所が施設外就労を導入するにあたってのメリットとデメリットを比較しながら、その意義や課題について具体的に解説します。
施設外就労を導入するメリット
1. 利用者にとっての実践的な就労体験ができる
施設外就労は、実際の企業や地域の現場で行われます。そのため、実践的な作業環境を体験できる点が大きなメリットです。また施設内作業に比べて作業の幅が広がり、人間関係の構築、コミュニティづくり、通勤の習慣、時間管理能力など、一般就労に必要なスキルを自然に身につけることができます。
2. 社会とのつながりが強まることで自律(自立)にもなる
外部企業や地域社会との接点を持つことで、利用者自身が「社会の一員として働く」意識を高めることができます。これは、自己肯定感や社会参加への意欲向上にもつながり、自律するための一歩とも言えるでしょう。
3. 事業所の収益拡大や利用者の工賃向上および地域連携の強化
外部からの作業委託契約または業務委託契約により、施設外就労を通じた新たな工賃収入の確保が可能になります。また、地域企業や自治体との協力関係を築くことは、作業所の存在意義や地域における信頼性を高める効果もあり、地域連携の強化につながります。
就労継続支援B型にとって施設外就労は「より社会に近い働き方」を提供する有効な選択肢です。利用者にとっての成長の機会は大きなメリットと言えます。そのため支援の質と安全性を両立させながら、現場での実践を広げていくことが重要でしょう。
施設外就労を導入するデメリット
1. 利用者の体調や能力に応じた配慮が必要
一般就労先での施設外就労の場合、社会の作業環境は、施設内に比べて柔軟性が低く、利用者のペースで進めることが難しい場面もあり、利用者の体調の変化や障害に対しての特性への配慮が難しい場面もあります。利用者に無理をさせてしまうことで、体調を崩したり、就労への不安感や意欲の低下を強めるリスクもあります。
さらに、コミュニケーションの低下で人間関係の問題や企業とのトラブルにもなり得るので利用者への配慮は重要になります。
2. 職員の負担や管理体制の強化が求められる
施設外就労には、職員の同行や送迎、現場での支援、危機対応、緊急対応などの負担が大きくなる傾向があります。特に、複数の現場を同時に管理する場合、人員配置や安全確保に課題が起こりやすくなります。
3. 外部企業との連携リスク
作業内容や進捗に対する企業側がもとめる期待値と、利用者の実力との間にギャップがあると、トラブルや契約終了のリスクもあります。また、企業側に就業中の利用者の障害に対して特性への理解が不足している場合、適切な作業環境が確保できないことも考えられます。そうなると利用者、企業側どちらもフラストレーションがたまり連携が取れにくくなります。
就労継続支援B型作業所で施設外就労を導入する方法は?5つの手順で解説!
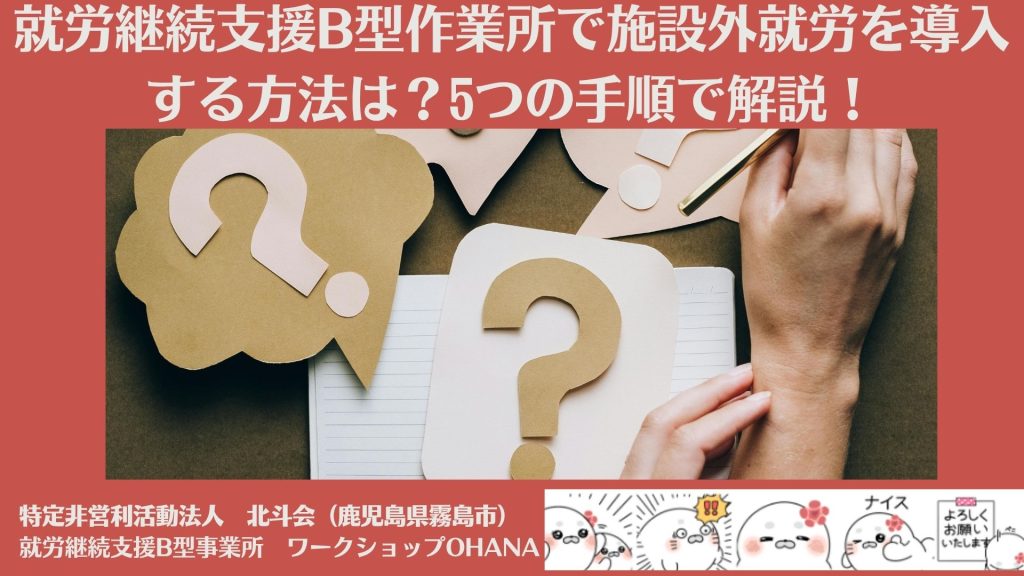
就労継続支援B型作業所において、利用者の社会参加や実践的なスキル習得、工賃向上などを目的として施設外就労を導入する事業所が増えています。

始めたいけど、どのような準備が必要なの?

企業との連携は?どう進めればよいのかわからない
など、実際の進め方が分からず悩む事業所も少なくありません。
下記では、施設外就労をスムーズに導入・運営するための基本的な5つの手順を、制度的な視点と実務的な観点の両面からわかりやすく解説します。新たな支援の選択肢として、利用者の工賃向上を目標とした支援の拡充などから施設外就労の導入を検討している事業所関係者の方は、ぜひ参考にしてください。
手順①|施設外就労の仕組みを作業所全体で把握する
施設外就労の導入にあたって最初に行うべきことは、施設外就労そのものの制度的な位置づけや運用ルールを、職員全体で正しく把握し理解することです。
施設外就労とは、就労継続支援事業所が企業から仕事を受注し、利用者がその企業の事業所内で、事業所の職員の支援を受けながら働く仕組みです。利用者のスキルアップや一般就労への移行を目的としています。施設外就労は、事業所内での作業とは異なり、外部企業との連携や利用者の安全管理、支援の記録など、求められる対応が多岐にわたります。
厚生労働省のガイドラインや自治体の通知を参照しながら、サービス提供責任者、職業指導員、生活支援員、管理者などが共通認識を持つ場を設けることが重要です。
■理解すべき「制度上の基本ポイント」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 障害者総合支援法において、「施設外で行う就労支援」として明確に認められた取り組み。 |
| 対象者 | 通所しているB型利用者のうち、一定の作業能力・適性があると判断された方。 |
| 作業形態 | 外部企業との「請負契約」または「業務委託契約」に基づき、その企業の実際の業務を担当する。 |
| 支援体制 | 原則、職員が常時もしくは定期的に同行し、支援と安全管理を行う。 |
| 利用者への支給 | 施設外での作業も、通常のB型の報酬(工賃+給付)対象として扱われる。 |
■職員間で確認しておくべき実務的なポイント
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 作業内容の安全性 | 利用者にとって危険がないか(機械作業、薬品使用など) |
| 支援体制の確保 | 誰が同行支援するのか、緊急時の連絡体制 |
| 労務提供との違い | 雇用契約に該当しないよう、請負業務であることを確認 |
| 契約書の管理 | 契約内容の明確化と文書保存(自治体監査に対応) |
| 利用者への説明 | 就労内容や場所を利用者にも丁寧に説明し、同意を得る |
“全体での把握”が安全で効果的な施設外就労の土台になります。施設外就労は、就労支援の幅を広げる大きなチャンスですが、その一方で制度的な理解不足や現場間の連携ミスがあると、支援の質や安全性を損なうリスクも高い取り組みです。
だからこそ、導入にあたっては事業所全体で「なぜ」「どのように」「何に注意して」実施するのかを把握・共有しておくことがスタートラインとなります。
手順②|職業指導員と利用者の適性を確認する
実際の職場環境での作業を伴うため、利用者ごとの体調、能力、通勤手段、対人関係スキルなどを総合的に評価する必要があると同時に、指導にあたる職員側のスキルや配置体制についても確認しておきましょう。
個別支援計画やモニタリングの記録をもとに、「対象となる利用者がどのような環境で能力を発揮できるか」を丁寧に見極め適性の確認をはかることで、一般就労に移行した時のミスマッチ防止にもつながります。
施設外就労の場合、基本の施設内での就労と違い作業に対し、または人間関係など相談できる職員が限られてしまいます。そのため可能な限り指導員と利用者の関係が適正であり、普段から話しやすい関係性を構築しておくことが重要です。さらに言えば、作業の内容と環境によっては、同行する指導員は同性が好ましいでしょう。体調の変化など利用者は伝えやすくなりますし、安心感と信頼関係につながるためです。
手順③|適性に合った施設外就労先を探す
利用者の特性や能力に応じた施設外就労先を見つけるには、地域企業や農場、公共施設などへの働きかけが必要不可欠です。はじめは、B型作業所に理解のある既存の取引先や地域のネットワークを活用するのが効果的でしょう。

なぜ適性が重要なのかな?
就労継続支援B型事業所に通う利用者の多くは、精神・知的・身体などさまざまな障害や特性があり、個別の配慮事項を抱えています。そのため、本人のできることや苦手なこと、体調・集中力の波を考慮した上で、無理のない作業先を選定することが極めて重要になるためです。
たとえば、農業がしたい利用者に対してPC作業を促してもスキルアップにはつながりません。なぜなら、作業に強いストレスを感じてしまうと、継続性の低下、意欲低下の可能性や体調不良につながってしまう場合もあるためです。さらに、作業に対して不満がたまることでコミュニケーション不足となってしまい作業先とのトラブルや支援者との信頼関係が損なわれることもあります。そのため、作業内容と利用者の状態のマッチングを慎重に行うことが、施設外就労の成功につなるでしょう。
利用者の適性に合った就労先を探すことが重要となります。
つぎに現地または現場の見学をしてみましょう。見学により作業内容の確認ができ、利用者の負担にならないか、安全面は確保されているかなどをチェックできます。可能であれば、事前に職員が短時間でも作業を体験しておくと、よりリアルな支援計画が立てられます。
手順④|取引先と施設外就労契約を締結する
施設外就労先が決定したら、B型作業所と企業との間で請負契約や作業委託契約または業務委託契約を締結します。契約時は契約書で明記すべき主な項目の中でも重要な「就労支援の一環としての作業(※1)」であることを必ず明記し、雇用関係が発生しないことを明確にしておくことが必要です。
あわせて、作業内容・工賃の支払い方法・安全配慮・緊急時の対応や連絡先などについても書面で取り決めておきましょう。また契約書のフォーマットは、自治体や地域の就労支援センターが用意している場合もあるので確認し使用することも可能です。
就労が始まる前に企業側には事前に利用者の障害について説明し、利用者側には作業内容の説明をし理解してもらいそれぞれが準備しておきます。理解が深まり、お互いが内容の把握ができるとスムーズに就労へとつなげることができるでしょう。
※1)ほかにも施設外就労の契約書には、次のような内容を明記する必要があります。
- 作業内容と範囲(具体的に)
- 作業場所と時間帯
- 報酬の支払い方法・金額
- 成果の基準(請負の場合)
- 利用者に事故・ケガがあった場合の対応
- 責任の所在(作業中のトラブルなど)
【契約形態を選ぶ際の注意点】
契約形態は、業務内容や作業先の意向だけでなく、「支援として適切か」「制度の趣旨に合っているか」を踏まえて判断することが重要です。また、事業所の職員が利用者を適切に支援できるか、さらにそのための体制が整っているかということも前提となります。
最も注意したいのは、企業側が利用者を直接「社員のように」指導してしまう場合です。内容と場合によっては、雇用とみなされて法的問題が生じるリスクがあるためです。あくまで福祉サービスの一環として、就労継続支援B型事業所の職員が関与・指導する支援体制と職員の配置が必要不可欠となります。
手順⑤|施設外就労の開始
契約が整ったら、いよいよ施設外就労の開始です。初日は職員が必ず同行し、作業環境、トイレ・休憩場所、安全対策の確認を行います。利用者が安心して作業に取り組めるよう、丁寧な説明とフォローが必要不可欠です。
実施後は、支援記録の記入、工賃の処理、利用者や企業からのフィードバック収集を継続的に行い、必要に応じて支援方法や作業内容の見直しを進めましょう。可能なら固定の職員が安定して同行できることが最良ですが、実際困難であるため誰が見てもわかりやすい記録の記入、フィードバックをしておきましょう。
施設外就労は、利用者にとっての成長のチャンスであり、事業所にとっても地域社会との連携を深め、理解を得る好機です。ただし、導入には制度への理解・人的体制・企業との信頼関係の構築など、多角的な準備が求められます。
5つの手順を確実に踏むことで、施設外就労を「単純に外仕事」ではなく、「支援の質を高めるツール」として活用することが可能になるでしょう。
まとめ|就労継続支援B型作業所で施設外就労を導入すると仕事の幅が広がる!

就労継続支援B型作業所において、施設外就労を導入することは、単純に作業場所を外に広げるという意味だけではなく、利用者一人ひとりの「働く場の選択肢」や「成長のチャンス」を増やすことにつながります。
施設外就労ならではの魅力として、施設内では対応しきれないような実践的な作業や体験、人間関係・時間管理といったスキルを、自然と現場で身につけることができる点です。一般就労と違い利用者の障害を理解してもらったうえで、自身のペースで就労でき、また、事業所にとっても、地域企業との連携によって新たな業務を獲得し、仕事の幅を広げるチャンスとなります。施設外就労を利用する利用者の方は職員の支援、指導があるうちにさまざまなスキルの獲得をし、可能ならば資格取得などを目指すのもよいでしょう。
施設外就労の制度の理解や支援体制の構築には一定の準備が必要ですが、それを乗り越えることで、施設外就労は「支援の幅」だけでなく「未来の可能性」をも広げてくれる手段となるでしょう。支援の拡充は作業所側のメリットだけでなく、利用者にもメリットがあります。
さいごに、本記事について簡単にまとめました。
- 施設外就労とは、施設の外で働ける就労の現場
- 就労継続支援B型での位置付け
- メリットおよびデメリット
- 施設外就労の導入方法を5ステップで紹介
- まとめ
施設外就労の導入は、就労継続支援B型事業所にとっての「働く支援」を、よりリアルで豊かなものに変える第一歩です。
就労の機会に触れ、人から「ありがとう」「助かっているよ」など社会のなまの声を直接受け取ることで、利用者は自信やモチベーションが高まり、将来的な一般就労への意欲にもつながります。
就労継続支援B型作業所においても、施設外就労の導入は、大きなメリットをもたらす取り組みです。企業と連携することで、地域における福祉への理解が深まり、社会資源としての就労継続支援B型作業所の存在感が高まります。また、施設外就労先で信頼を得ることができれば、安定的に仕事を確保でき、工賃向上にもつながります。
さいごに、施設外就労が利用者、事業所双方から理解得られ、導入の実現のお手伝いができれば幸いです。
就労継続支援B型「ワークショップOHANA」にご興味・ご相談があれば、ぜひ下記までお問合せください。
特定非営利活動法人「北斗会」の連絡先はこちら
| 法人名 | 特定非営利活動法人 北斗会 |
| 代表理事 | 高野 和子 |
| 提供サービス種別 | 就労継続支援B型事業 |
| 施設名 | ワークショップOHANA |
| 住所 | 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央1丁目14-4 |
| 電話番号 | 0995-50-3236 |
| ファックス番号 | 0995-50-3075 |
| お問い合わせ先 | お問い合わせはこちら |
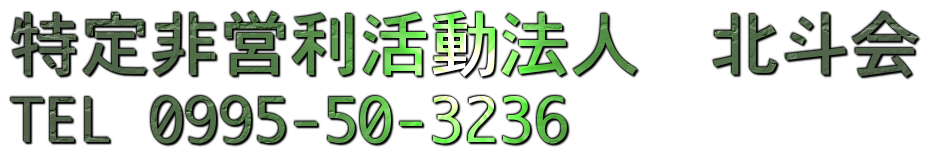
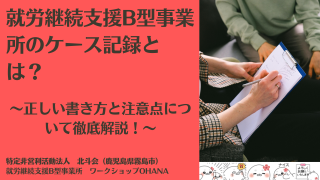
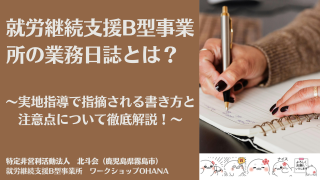
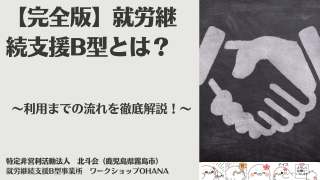
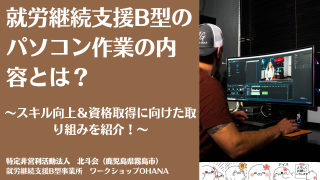
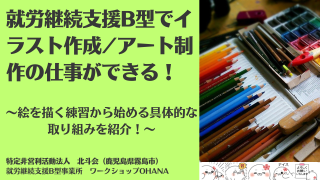

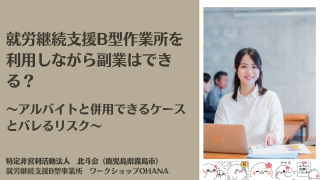
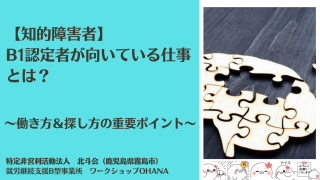
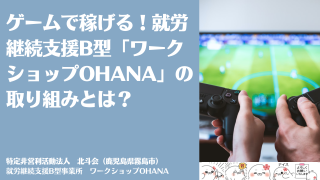
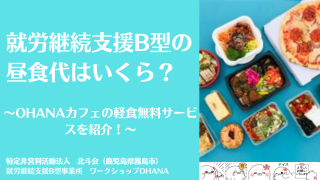
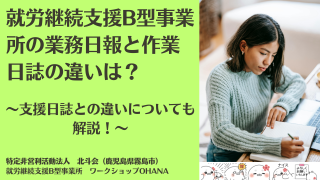
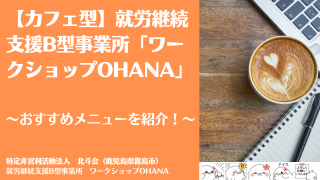
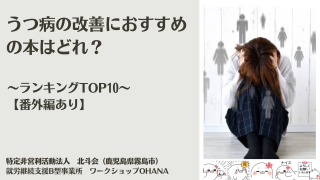
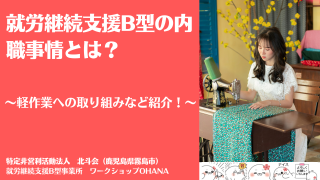
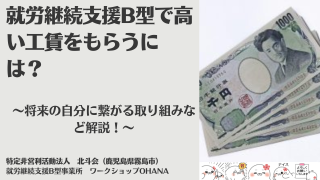
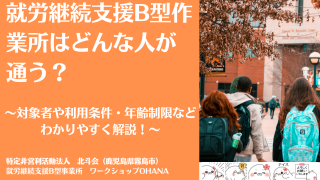
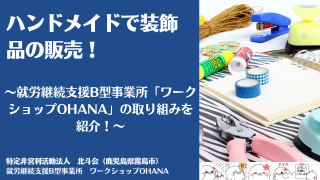
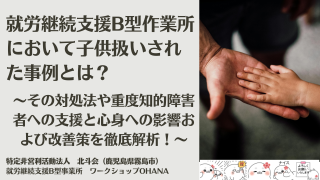
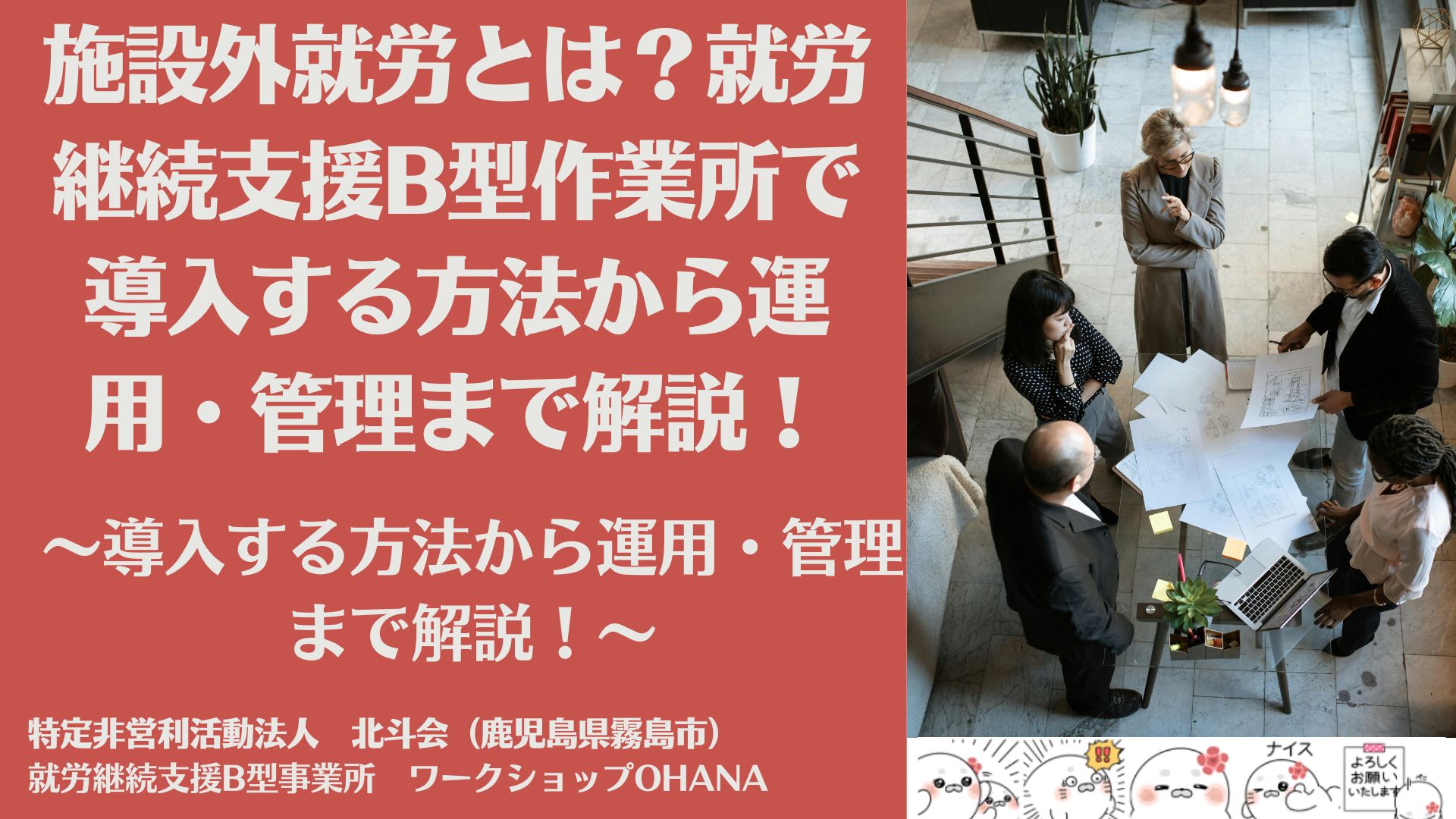


コメント