就労継続支援B型作業所を利用できる対象者は精神障害や知的障害、身体障害、難病などを抱えている18歳以上の成人で、障害者手帳を持っていればどんな人でも通うことができます。
原則として、18歳未満の未成年は就労継続支援B型作業所を利用できないため注意しましょう。
また、就労継続支援A型作業所とは違い、就労継続支援B型作業所は利用者との雇用契約を結ぶことはありません。

就労継続支援B型作業所ってどんな人が通うの?

どんな障害でも利用できるの?対象者や年齢制限は?

就労継続支援B型作業所ではどんな仕事をしているの?
このように就労継続支援B型作業所に興味がある人、どんな人が通っているのか気になる人もいるのではないでしょうか。
就労支援B型作業所は18歳以上という年齢制限はありますが、精神障害や知的障害、身体障害、難病などを抱えており、障害者手帳を持っていればどんな人でも通うことが可能です。また、精神障害の場合は、統合失調症や拒食症など、具体的な医師の診断書があれば利用できます。
本記事では、就労継続支援B型作業所はどんな人が通うのか?具体的な対象者や利用条件、年齢制限などについて詳しく解説しています。また、精神障害者や知的障害者、身体障害者などの特徴や利用に際しかかる費用・仕事内容・工賃受給までの手順なども紹介しています。
最後まで読めば、下記の内容を理解できます。
- 就労継続支援B型作業所はどんな人が通う?【結論:障害者】
- 利用できる対象者/利用条件/年齢制限【結論:18歳以上の成人で障害認定を受けている人】
- 就労継続支援B型作業所の利用料金【結論:0円~37,200円】
- 就労継続支援B型作業所の仕事内容と工賃をもらうまでの流れ
- 自分に合った就労継続支援B型作業所の選び方
就労継続支援B型作業所では、どんな人が通っているのか?興味がある人は必見です。
ぜひ、最後までご覧ください。
就労継続支援B型の仕組みをさらに詳しく知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。
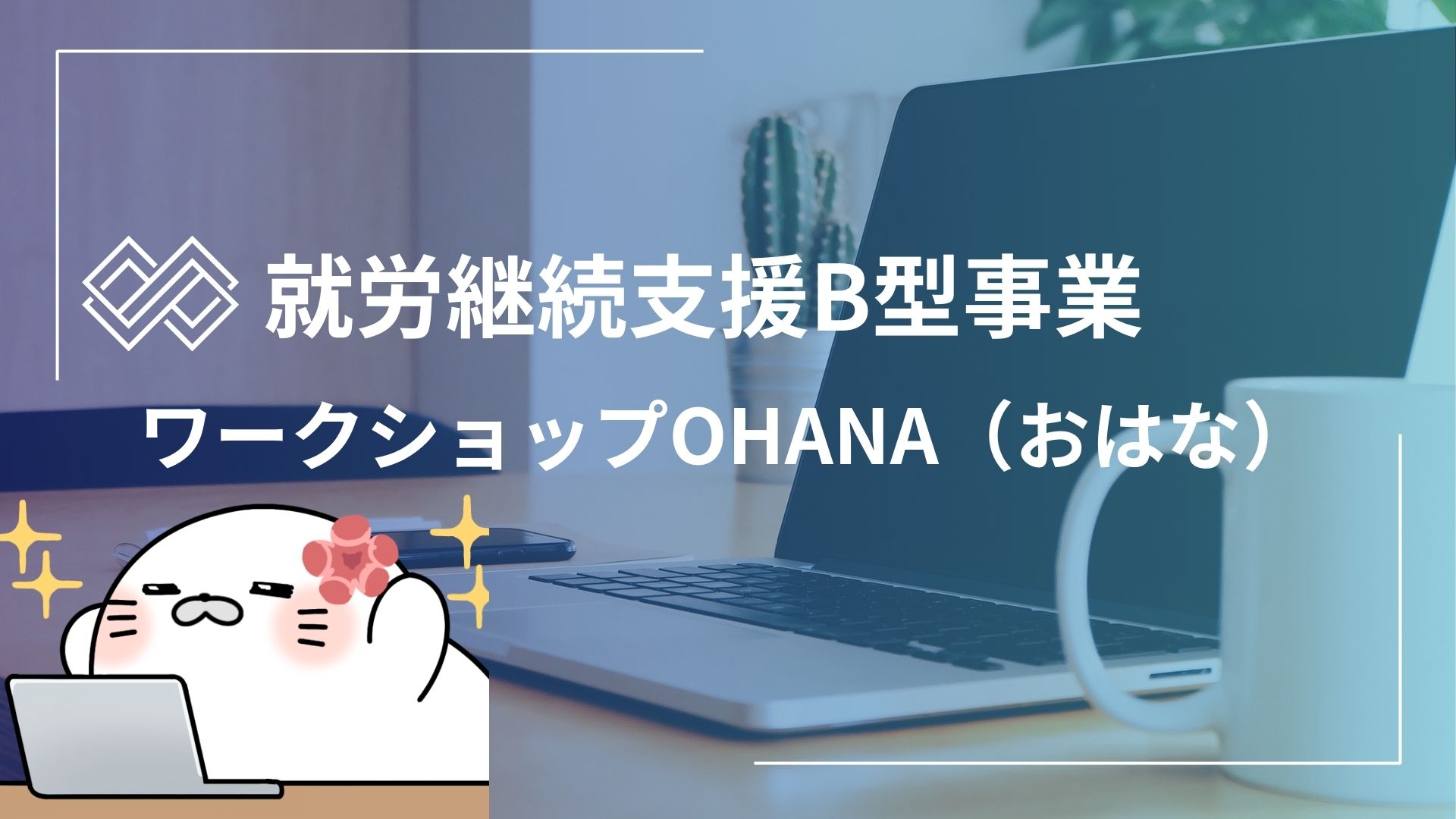
- 就労継続支援B型とは?対象者はどんな人?
- 就労継続支援B型作業所はどんな人が利用できる?対象年齢や利用期間などの条件をわかりやすく解説!
- 就労継続支援B型作業所を利用してどんなメリットがある?知っておくべきデメリットについても解説!
- 就労継続支援B型ではどんな仕事ができる?作業内容と工賃をもらうまでの流れを紹介!
- 就労継続支援B型とA型の違いは?就労移行支援との連携について解説!
- 就労継続支援B型作業所を利用するまでの流れは?どんな人が対象者か確認して通所するまでの手順を解説!
- 自分に合った就労継続支援B型作業所の選び方は?どんな視点で見極める必要があるのか7つのポイントで解説!
- 【Q&A】就労継続支援B型はどんな人が通う?対象者は?
- まとめ|就労継続支援B型は幅広い年齢層と障害を持った人が自分のペースで利用できる場所!
就労継続支援B型とは?対象者はどんな人?

就労継続支援B型とは、作業所(事業所)と利用者(障害者)が直接雇用契約を結ばずに就労支援を受けることのできる障害福祉サービスのこと。就労継続支援A型作業所とは違い、利用者自身が自由度の高い仕事をできるところが魅力です。
就労継続支援B型作業所で仕事をすると、その対価として工賃をもらえます。
でも、就労継続支援B型作業所って、実際どんな人が通うの?
このように、気になるという方もいるでしょう。
利用者とは直接雇用契約は締結しない非雇用型の就労形態を持つ就労継続支援B型ですが、ここでは具体的に対象者や利用条件、対象年齢などをわかりやすくまとめました。
それでは、詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型作業所を利用できる対象者
就労継続支援B型作業所を利用できる対象者がどんな人なのか、厚生労働省が定めた概要を下記にまとめました。
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
- 50歳に達している人又は障害基礎年金1級を受給している人
- 1及び2に該当せず、就労移行支援事業者等による評価により、就労面に係る課題等の把握が行われている人
わかりやすくいうと身体障害や精神障害もしくは、年齢的に一般の企業やA型事業所での就労をすることが難しい人や、障害基礎年金1級を受給している人・就労移行支援事業所などで仕事をする際の課題や提案(アセスメント)が把握されている人が利用対象に該当するということです。
厚生労働省が定めた概要の詳細については、下記リンクから確認できます。
次に、どんな人が就労継続支援B型作業所を利用できるのか、詳しく解説していきます。
身体障害
身体障害とは、先天的・後天的な理由で、身体機能の全部あるいは一部が不自由な状態を言います。
これでは解釈が難しいので、身体障害をさらにわかりやすく説明すると、身体障害者福祉法により、下記の5種類に区分されます。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 内臓機能などの疾患による内部障害
いずれかの障害がある場合は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
知的障害
知的障害とは、精神遅滞とも呼ばれている知的・発達障害です。
倫理的思考・問題解決・計画・抽象的思考・判断・学校や経験での学びのような精神機能の障害が特徴の発達障害のひとつです。
さらに、「知的障害」「発達障害」も大枠としては、精神障害に含まれます。
精神障害
精神障害とは、精神疾患のため精神機能の障害が生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のこと。症状が悪化すると、判断する力や行動のコントロールする力が著しく低下することがあります。
例えば、統合失調症やうつ病、双極性障害、不安性障害などの精神疾患から生じる障害のことをまとめて示す場合があります。
精神疾患から生じた障害により感情のコントロールができなくなると、不安性障害の場合、公共の場等の狭い空間でパニックになることもあります。
精神障害は、精神疾患と明確な区別はされていませんが、精神疾患から生じる障害のことを指す場合が多いです。
発達障害
発達障害とは、脳機能の発達に関係する障害です。
生まれつき一部の脳機能の発達が遅れるなど、幼いころから行動面や情緒面に特異的な特徴がある状態をいいます。
そのため保護者が育て方の悩みを抱えたり、こどもが生きることの辛さを感じたりすることもあります。
発達障害は、広義の精神障害に含まれており、下記のとおり分類されます。
- 自閉症スペクトラム障害
- 学習障害
- 注意欠如多動性障害 など
社会性や読字・書字、注意力等に関わる脳機能の障害が想定され、その症状が通常低年齢において発現するものです。
また、成人期になってから仕事や家庭などで支障をきたし、支援が必要な場合もあります。人によってさまざまな症状の現れ方がありますが、落ち着きがないなどの多動性・衝動性は軽減する場合があります。
さらに、不安や気分の落ち込みや気分の波などの精神障害を伴うこともあります。
難病
難病とは、治療をすることが難しく慢性の経過をたどる疾病のことで、今の医療でも存在します。
一般的には、このような疾病を難病と呼んでいます。
ただし、完治はしないものの適切な治療や自己管理を続ければ、日常生活への支障を最小限にできる状態になる疾患が多くなっています。
現在では、特定疾患として、123種類の疾患が指定されてます。
ちなみに、就労継続支援B型作業所によっては事業開始申請時に提示する障害の種類で「難病者」の受け入れを指定していないケースもあります。
難病者に限っては利用できないケースもあるため、事業所に対して事前に利用できるかどうか確認しましょう。
就労継続支援B型作業所はどんな人が利用できる?対象年齢や利用期間などの条件をわかりやすく解説!

就労継続支援B型作業所はどんな人が利用できるのか、対象者となる障害の種類については理解できたでしょう。
補足ですが、障害者手帳がなくても病院からの診断書があれば、就労継続支援B型作業所を利用できるケースがあります。
つまり、就労継続支援B型作業所を利用する際に、必ずしも障害者手帳が必要というわけではないということ。自治体により判断が異なりますが、医師から障害への診断を受け、定期的に通院していることを示す通院証明でも就労継続支援B型制度を利用することが可能な場合もあります。
次に、就労継続支援B型作業所における利用条件や利用者の年齢制限・利用期間・料金(自己負担金)について解説していきます。
まずは、就労継続支援B型作業所の利用条件から詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型作業所の利用条件
就労継続支援B型作業所の利用条件とはどんな内容なのか、わからない人や気になる人もいるでしょう。
ここでは、就労継続支援B型作業所の利用条件について解説していきます。
身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている人が就労継続支援B型の主な対象となります。
具体的に対象者はどんな人なのか、下記に事例をまとめました。
- 就労の経験はあるが、現在は障害の症状の悪化など事情があって一般企業への就労が難しい方
- 就労移行支援制度を活用したが、雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校などを卒業して、就労活動を行なったが一般企業への就労に結びつかなかった方
- サービス管理責任者のアセスメントにより就労面の課題が把握されている方
- 障害基礎年金1級を受給している方
それぞれの事例について、詳しくみていきましょう。
就労経験があり障害の程度悪化が原因で一般企業への就労は難しい方
過去に一般企業での就労の経験があって、身体障害・精神障害・その他の病気などの事情により、一般企業への就職や転職が困難になったケースです。
就労移行支援制度を活用しても雇用に結びつかなかった方
就労移行支援制度とは、障害者自立支援法のもと、就労を希望する障害のある方を企業などの就労につなぐ事業として2006年につくられた仕組みのことです。
就労移行支援制度を利用しても、雇用には至らなかったケースです。
特別支援学校の卒業後に一般企業への就職に結びつかなかった方
特別支援学校を卒業後に就職活動を行い、一般企業での採用を目指したにもかかわらず結びつかなかったケースもあります。
サービス管理責任者のアセスメントにより就労面の課題が把握されている方
障害福祉サービスを提供する事業所において、適切なサービスが提供できるように全体的な管理を行うのがサービス管理責任者です。
サービス管理責任者は、就労継続支援B型作業所を利用する際、対象者にアセスメントを実施して就労面の課題を整理します。
これによって、就労継続支援B型作業所の利用者の就労する際の課題が把握されているケースもあります。
障害基礎年金1級を受給している方
障害者手帳の等級とは異なり、日本年金機構の障害等級表に定める1級または2級に該当していることが障害基礎年金受給要件の1つです。
障害のある人でも就労継続支援B型作業所の利用対象外になるケースもあるため、注意が必要です。
日本年金機構の障害等級表は、下記リンクから確認できます。
就労継続支援B型作業所の対象年齢
就労継続支援A型事業所には、基本的に18歳以上65歳未満という年齢制限があります。
一方で、就労継続支援B型の対象年齢については18歳以上と決まりはありますが、年齢の上限に制限はありません。
65歳の高齢者でも、就労可能と行政から判断されれば就労継続支援B型作業所を利用できます。
しかし、特別支援学校などの学校を卒業後、そのまま利用することはできないと定められているので注意が必要です。
就労継続支援B型を利用する対象の特例として学校卒業後、1度でも就労継続支援A型事業所や一般企業で就労をしており、前述した利用条件に当てはまれば、利用できます。
通所後に発生する利用者負担金(利用料金)
就労継続支援B型作業所を利用するにあたって、利用者負担金(利用料金)が気になる方もいるでしょう。
前年度所得に影響しますが、前年度の年収が200万円未満であれば、就労継続支援B型作業所の利用料金は実質無料(0円)です。
基本的には訓練等給付費という形で、国や自治体(市町村などの行政)から負担されます。
まずは、利用料金における国の制度や利用者負担金(自己負担金)について、詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型作業所における利用料(=利用者負担金)の詳細と厚生労働省の公式見解については、下記の記事でわかりやすく解説しています。
利用料金における国の制度
週継続支援B型作業所を含む就労継続支援事業所は、自治体から訓練等給付費として給付金が支給されているため、利用対象者の人は赤字にならず多くの人が無料(0円)で利用できます。
ただし、就労継続支援B型作業所の利用料金は前年の世帯所得の額により変わる場合があるので注意しなければなりません。
利用料金と自己負担金の区分
就労継続支援B型作業所の利用料金(利用者負担金)は、厚生労働省の「障害者の利用者負担」により定められています。
その概要を、下表にまとめました。
| 世帯収入状況 | 1か月あたりの利用者負担金の上限額 |
| 生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯(年収0円~200万円未満) | 0円 |
| 市区町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外(所得割16万円以上) | 37,200円 |
厚生労働省の公式発表では「概ね」と記載されていることから、利用者の生活状況と行政の判断により分類が決定されることがあります。
就労継続支援B型作業所を利用できる期間(期限)
就労継続支援B型作業所を利用できる期間や有効期限は、障害福祉サービス受給者証に記載されます。
初めは就労継続支援B型作業所の利用開始前に行う担当者会議で利用開始日が決定し、その後は定期的にモニタリングもしくは期間(期限)更新月に行われる担当者会議で継続の有無が決定します。
基本的には利用者の誕生月に障害福祉サービス受給者証の更新となり、障害の程度により「3か月間」「6か月間」「1年間」で期間(期限)が定められます。
就労継続支援B型作業所を利用してどんなメリットがある?知っておくべきデメリットについても解説!

就労継続支援B型作業所には、どんなメリットがあるのでしょうか。
その1つに、就労継続支援事業の社会的な需要を満たせることが挙げられます。
厚生労働省が公開した「障害者の就労支援対策の状況」によると、令和2年3月時点で就労継続支援B型作業所を利用している人数は全障害者数約964万人中、約3%の約26.9万人と推計されています。
また、障害者のなかには就労継続支援事業所を利用したくても、利用方法が分からず利用できていない人もいるのではないでしょうか。
就労継続支援を必要とする人はこれから増加傾向になることが予測されます。
それでは就労継続支援B型作業所を利用して、どんなメリットやデメリットがあるのか、その概要を下表にまとめました。
| 就労継続支援B型のメリット | 就労継続支援B型のデメリット |
| ・自分の体調や体力に合わせたペースで働くことができる・作業所によっては1日1時間や週に1日だけの利用が可能・短時間でも生産活動に携わりたい人や社会参加を行いたい人に向いている・利用期間や利用者年齢の上限の制限がない | ・工賃の安さ・1日あたり長時間の生産活動はできない・作業の物足りなさを感じることがある・就労に繋がるスキルが習得できていないと感じるときがある |
それでは、詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型作業所を利用するメリット
就労継続支援B型作業所を利用するメリットについて、下記にまとめました。
- 自分の体調や体力に合わせたペースで働くことができる
- 事業所によっては1日1時間や、週に1日だけの利用が可能な場合もある
- 短時間でも生産活動に携わりたい人や、社会参加を行いたい人に向いている
- 利用期間や利用者年齢の上限の制限がない
また、過去に一般企業で就労した経験があっても現在は働いておらず将来的に再度、一般企業での就労を目指したい人や就労継続支援A型事業所での雇用型勤務を希望している人も、
訓練も兼ねて就労継続支援B型作業所を利用することができます。
就労継続支援B型作業所のデメリット
就労継続支援B型作業所のデメリットについて、下記にまとめました。
- 工賃の安さ
- 1日あたり、長時間の生産活動はできない
- 作業の物足りなさ・就労に繋がるスキルが習得できていないと感じる場合がある
厚生労働省が公表している「令和3年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援B型作業所における令和3年度の全国平均工賃は月額あたり16,507円となっており、決して高額とはいえません。
しかし、体調や能力の向上により利用時間を増やしたり、作業効率を上げたりすることにより平均以上の工賃をもらうことも可能です。
就労継続支援B型作業所で高い工賃をもらう方法とコツについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
就労継続支援B型ではどんな仕事ができる?作業内容と工賃をもらうまでの流れを紹介!

就労継続支援B型作業所では、どんな仕事があるのでしょうか。
結論をいえば内職や手工芸品、装飾品を制作する軽作業から農作業などの重作業まで幅広い仕事があります。また、作業所の外に出て働く「施設外就労」という仕組みもあります。
ここでは、就労継続支援B型作業所で仕事をして工賃をもらうまでの流れの概要をまとめました。
- 就労継続支援B型作業所と利用契約を締結して通所する
- 仕事(作業)に取り組む
- 仕事量もしくは作業量に応じて、毎月工賃をもらう
大まかには、上記の手順で工賃をもらえます。
就労継続支援B型の仕事内容は、各作業所によって違います。
例えば、パソコンでの作業や農作業などさまざまな内容があるため、自分にあった作業所をみつけましょう。
そのために重要なことは、自分が希望する仕事内容や気になる事業所への問合せ、そして見学をすることです。
また、出勤日数や出勤時間によっても仕事内容・工賃計算・工賃支払日は異なります。
特に工賃の支払日は、それぞれの就労継続支援B型作業所によって異なる場合があるため、利用する前に必ず確認しましょう。
下記の記事では、鹿児島県霧島市に所在する就労継続支援B型作業所「ワークショップOHANA」の仕事内容と工賃をすべて公開していますので、ぜひ参考にしてください。
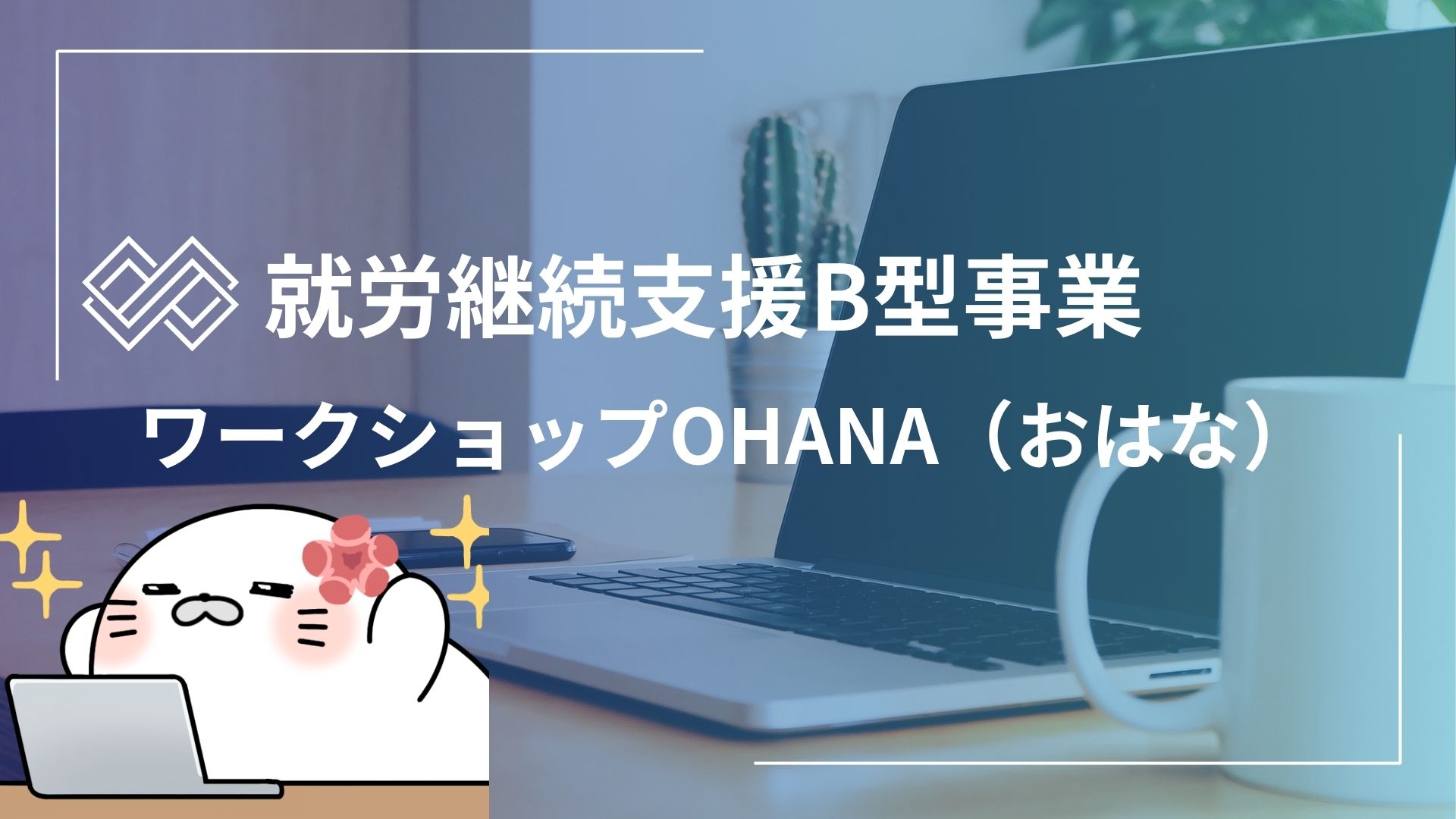
それでは、一般的な就労継続支援B型作業所の仕事内容(作業内容)から詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型作業所の仕事内容
就労継続支援B型作業所は日本全国にあるため、地域性や規模の違いなどから仕事(作業)の内容が異なる場合があります。
基本的には、アクセサリー作りなどの室内での軽作業を行っているイメージが強い就労継続支援B型作業所ですが、実はさまざまな仕事ができます。
原則として約1時間~5時間の範囲(作業所の重要事項説明書の記載による)で、なるべく精神的・身体的に負担がかからない程度とされており、障害者によっても作業時間の長短が選べます。
就労継続支援作業所の仕事内容の事例を、下記にまとめました。
- 事業所内での簡単なデータ入力
- 工場内でパッキングやピッキング
- 仕分けや書類整理など
- 農作業
- 部品加工
- 手工芸品作成
- 事業所運営のカフェやレストランのホール
- クリーニングや清掃作業 など
それぞれの作業事例について、詳しくみていきましょう。
事業所内での簡単なデータ入力
電子化されていない伝票・文書・名簿・アンケートなどをExcelなどを活用して簡単なデータ入力などがある場合もあります。
工場内でパッキングやピッキング
工場内で梱包したり、出荷に必要な商品を各置き場から集めてくる作業のことです。
仕分けや書類整理など
事業所の仕分けや書類整理などの比較的しやすい軽作業です。
農作業
水耕栽培や野菜販売などの農作業を作業内容としている事業所もあります。
部品加工
自動車部品の加工や水道関連部品の加工などが、主な例として挙げられます。
手工芸品づくり
作業所によっては、小物入れやキーホルダーなどの手工芸品作りをしている場合もあります。
事業所が運営するカフェやレストランのホール
カフェやレストランのホールが併設されている作業所の場合、事業所を主体として運営しているカフェやレストランのホールで接客や配膳などの作業がある場合もあります。
クリーニングや清掃作業など
洋服のクリーニングやコインランドリーの清掃作業などを作業の1つとして取り入れている作業所もあります。
この他にも違う仕事内容の事例もあるため、利用する対象者自身に合った作業を選ぶ・試行をしてみることが重要といえます。
外出が困難な場合の就労について
就労継続支援B型作業所では、何らかの事由により外出が困難な場合がある人、または市区町村が在宅支援を許可している場所に所在地がある場合のみ在宅就労が可能です。
在宅就労の対象者について下記にまとめました。
- 在宅サービスを希望している人
- 市区町村が在宅サービスによる支援が必要と判断された人
- 相談事業所により在宅ワークの必要性が認められた人
外出が困難な場合、在宅でも就労支援のサービスを受けることができますが、利用する就労継続支援B型作業所の在宅就労運営ガイドラインが独自に設けられていなければなりません。
そのため、就労継続支援B型作業所の在宅支援を希望の場合は、事前に在宅支援が可能かどうかの確認をすることをおすすめします。
就労日数と就労時間
就労継続支援B型を利用したいと考えたら次に気になるのは就労日数と就労時間でしょう。就労継続支援B型では利用者の障害の度合いや体調に応じて、本人の負担にならない自由なスタイルで利用可能です。
就労継続支援B型の特性から、利用者の希望に応じて1日2〜4時間ほどの勤務時間から1週間に1回午前中、他にも平日の1時間だけといった短時間の利用もできます。
働く時間は長くても1日8時間・週40時間以内で、休日も最低1〜2日はあります。
厚生労働省の規定資料にも、就労継続支援B型は出欠・作業時間が利用者が自由に選択できることがしっかり明記されているので、利用するときはしっかりと自分の希望をつたえ就労のスタイルを決めるといいでしょう。
参考:就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について
自身の体調にあわせ、就労日数・就労時間の途中変更も可能ですが、その際は相談事業所とB型作業所に相談しアセスメントの変更が必要となるので注意しましょう。
利用後に工賃をもらうまでの流れ
利用者は、雇用契約を結ばずに仕事をするのが就労継続支援B型の特徴です。
しかし、作業所によっては1日の工賃が定額制の場合や作業をした分の歩合制など、工賃の支給方法に違いがあることがあります。
工賃の決め方は、基本的に就労継続支援B型事業所によって異なるため、利用する際は確認したほうがよいでしょう。
雇用契約を結ばずに仕事をするのが就労継続支援B型の仕組みでもあるため、労働基準法の最低賃金は適応されません。
その代わり、障害者総合支援法に記載されている最低工賃月額の3,000円は少なくとももらえるでしょう。
「就労継続支援B型作業所のデメリット」でも前述したとおり、就労継続支援B型作業所の全国平均工賃は月額で約15,000円のため、時給換算で約160円となります。
就労継続支援B型作業所を利用して工賃をもらうまでの具体的な流れを、下記にまとめました。
- 作業所との契約ご利用開始
- 出来高・時給・日給など工賃計算方法を確認
- 作業内容と作業所が提示している工賃の確認
- 自分の出来る作業がどのくらいの工賃なのか確認・相談
- 目標としている工賃額の要望相談
- 作業開始、作業内容の把握
- スキルアップによる工賃アップを目指す
- 利用分の工賃発生・作業所工賃支払い
工賃を貰うまでにはまず作業所を見つけ、契約し利用する必要があります。工賃の支払い方法はそれぞれ就労継続支援B型作業所によりさまざまです。
時給制・日給制・月給制(基本給+出来高)などがあります。利用する作業所の工賃計算方法を見聞きし、その中で自分の希望する作業内容を見つけ、工賃の希望額と利用方法を相談し決定します。作業効率が上がると目標工賃に近づくことができるでしょう。目標工賃に向けて自分に負担がなく、継続して利用できスキルアップを目指せるのが重要といえます。
もちろん工賃アップを目指すことも可能です。そのためには、スキルアップ、資格取得など目標工賃に近づく方法を作業所と話し合い、無理なく継続出来る範囲で決めていきましょう。
就労継続支援B型とA型の違いは?就労移行支援との連携について解説!

就労継続支援B型と同じ就労系障害福祉サービスには、「就労継続支援A型」「就労移行支援」があります。
就労継続支援B型とA型、そして就労移行支援は仕組みや構造が全然違いますので注意しましょう。
就労系障害福祉サービスの仕組み上、就労継続支援B型とA型を併用したり、就労移行支援と併用したりすることはできません。
それでは、就労継続支援系サービス(A型・B型)と就労移行支援との違いを、下表にまとめました。
| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | |
| 目的 | 一般就労に向けた知識とスキルを身につける | 将来自律できるように就労訓練によりスキルを身につける | 就職するために必要な知識とスキルを身につける |
| 利用期間 | 制限なし | 制限なし | 原則2年間 |
| 対象者 | 一般企業への就労が困難または不安な方 | 一般企業への就労が困難または不安な方 | 就職を希望する方 |
| 年齢制限 | 18歳以上~上限なし | 18歳以上~上限なし | 18歳~65歳未満 |
| 雇用契約 | あり | なし | なし |
| 工賃(賃金) | 平均月収約7万円 | 平均月収約1.5万円 | 一部事業所を除いてなし |
| 利用料金 | 0円~37,200円 | 0円~37,200円 | 0円~37,200円 |
ちなみに、就労系障害福祉サービスの併用には例外があり、2つの就労継続支援B型作業所を同時に利用できるケースがあります。
ただし、事前に障害福祉サービス受給者証の発行元である市町村(行政)の許可が必要ですので、希望する場合には相談支援事業所の相談支援専門員に理由を説明したうえで手続きを進めてください。
それでは、就労継続支援B型と就労継続支援A型、就労移行支援の特徴から詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、精神障害や身体障害、知的障害、難病を抱えている人及び、年齢、体力などの理由で長時間の労働や雇用契約を結んで働くことが困難な人が対象となります。
就労継続支援B型には利用期間、年齢の上限に制限はありませんが18歳以上が利用対象とされています。作業内容については、利用者の障害の程度や体調、年齢に合わせて、トレーニングや就労経験をつみ能力向上を目指すことができるでしょう。
1日1時間から、1週間に1回など自分に負担のない利用が可能な就労継続支援B型事業所もあるので、自分のペースで働くことができます。自分の働きやすいスタイルをみつけることも重要です。
就労継続支援B型は雇用契約を結ぶことはないので収入形態が給料ではなく工賃となります。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、利用者の年齢の上限はありませんが、18歳以上でないと利用が出来ません。例えば特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、障害者雇用や一般就労での就職が難しかったり出来なかった人や、一般就労をしていたが体調面、精神面、障害の進行や変化、難病などにより就労が困難になった人が雇用契約を結んで利用できる特徴があります。
就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いについて詳しく解説していきます。
就労継続支援B型と就労継続支援A型の代表的な違いは雇用契約の有無でしょう。
就労継続支援B型はA型と同じく、一般企業への就労が困難な障害を持つ人や難病を抱えている人が主な利用者ですがA型では、比較的長時間の就労と安定した作業動作が求められることも特徴といえます。
就労継続支援A型は一般企業と利用者が雇用契約を結び、障害者雇用枠で仕事をします。就労継続支援A型は雇用契約を結び働くため、収入形態は報酬や給料という形で受けとることも特徴です。逆に就労継続支援B型は工賃といわれる収入形態になるのでもらえる金額についてもA型B型で差が出ることもあります。
就労継続支援B型は長時間働くことが難しい人や精神面、体調面で不安な人が自分のペースでゆっくり働くのに向いてますが、A型はある程度決まった時間で安定して仕事をすること、また繰り返し行うことができる人に向いているでしょう。
就労継続支援A型の利用者は就労経験をかさねるなかで、スキルを習得しスキルアップをして、就労への自信と安定を目的とし最終的に一般企業への就職・就労を果たすことが目標及び目的となります。
就労移行支援
就労移行支援とは、簡単にいうと就職・就労に向けてガイドをしてくれる福祉サービス事業所です。就労継続支援A型、B型と違い賃金や工賃の発生はありませんが就職・就労にむけて本人の希望する職種や職場の見学、体験ができるところが特徴でしょう。
就労移行支援と就労継続支援には大きな目的の違いが2つあります。まず就労移行支援には原則2年以内と利用期間に制限がありますが就労継続支援には利用期間の制限がありません。次に就労継続支援は働く場を提供する事が目的ですが、就労移行支援は一般企業への就職・就労と職場への定着をサポートする事が目的です。
一般的に就労移行支援作業所を通じ就職活動をしてみたが、現在の自分には一般就労は困難と感じ、短時間自分のペースで就労をしたいと考えの人は就労評価後に就労継続支援B型、A型の通所利用を選択することが多く見受けられます。
反対に就労継続支援B型、A型からステップアップし就労移行支援作業所を利用する人も一定数います。どちらの利用方法も就労移行支援の利用に対し目的を明確にすることが重要でしょう。
就労継続支援B型から生活介護への移行
就労継続支援B型から生活介護への移行について解説していきます。まず移行は出来ますが、生活介護と就労継続支援では提供時間の縛りと同日利用が出来ないことがあるので注意が必要です。
生活介護とは、重度の障がいを抱える人に対し、日中に生活的介護や生活・生産活動と生産場所の提供をサービスの中心としています。就労継続支援は就労場所の提供や就職支援、資格取得のサポートなどを行っています。
生活介護では、生活支援員を中心に、日常動作のリハビリなども行うため理学療法士などのリハビリテーション職も多く働いているのも特徴です。
就労継続支援事業所は、職業指導員や就労支援員など就労に関する職種が多く働いています。就労継続支援B型を利用する人は主に一般企業への就労が難しい障がいや難病を抱える人が利用しています。
リハビリが必要な人は、在宅での就労継続支援B型の利用も在住の市区町村の規定に合致すれば利用が出来ますが、生活介護は通所が必ず必要となります。移行を考えているときは現在の自分の体調で通所が可能か、送迎の方法(自分で確保するのか、作業所からの送迎の有無)など確認をしましょう。
生活介護を利用し一定基準以上の力をつけ一般企業への就労を目指すことも可能です。
その場合は、就労移行支援制度という別の制度を利用することを視野にいれます。この就労移行支援制度は就労移行支援事業所で利用することができます。
対象となるのは一般の会社や企業への就労を目指す様々な障害や難病を持つ人、そして18歳以上、64歳までの人です。
障害を持つ人でも、事業所職員が仕事内容に関連するビジネススキルの習得やビジネスマナーなどのカリキュラムを用意してくれるため、安心して制度を利用するとよいでしょう。
就労移行支援事業所はハローワークなどとは違い、直接求人を紹介することはありません。ですが、就職・就労活動のサポートや職場定着の支援をしてくれます。
就労移行支援事業所を利用する2年間の間、支援してくれるため心強い味方となるでしょう。
生活介護は日中のみの利用制限があり通所することが必須
ここまで生活介護と就労継続B型について解説しましたが、注意すべきことがあります。
就労継続支援B型を利用しつつ生活介護の併用についてです。必要性が認められれば 併用は可能です。ただし、同日の併用はできません。例えば、日中生活介護の利用をし午後から就労継続支援B型の利用は不可となります。
生活介護は生活・介護フォローが必要でありながらも社会への参加・貢献・就職に向け生産活動又は生産活動の機会を提供する福祉サービスです。就労継続支援B型から生活介護への移行を考えている人は、自分の体調や抱えている障害、難病の症状・状態をしっかり把握し、家族、作業所への相談を明確に行いましょう。
就労継続支援B型作業所を利用するまでの流れは?どんな人が対象者か確認して通所するまでの手順を解説!

初めて就労継続支援B型やA型、就労移行支援の利用を申し込む際には、まず各市町村の障害福祉窓口やハローワーク、地域の障害者基幹センターに相談しなければなりません。
もし、すでに相談支援事業所の相談支援専門員が担当としてついている場合は、その方に相談するのもよいでしょう。
就労継続支援B型作業所の利用を検討されている方の問い合わせ先を、下記にまとめました。
- お住まいの市町村役場(【「地域名〇〇」 障害福祉課】で検索)
- ハローワークの障害者向け就労支援(外部リンク)
- お住まいの地域の障害者基幹相談支援センター(【障害者基幹相談支援センター 「地域名〇〇」】で検索)
市町村の障害福祉課と障害者基幹相談支援センターの検索方法についても、下記のイメージです。
このように、インターネットの検索エンジンで調べたり、直接気になる事業所に問い合わせたりしてもよいでしょう。
就労継続支援B型作業所の経験豊富な担当者が丁寧に教えてくれます。また、あなたに最適な制度やカリキュラム、働く環境を提案してくれるでしょう。
ここまで、どんな人が就労支援B型作業所の対象者なのか、どんな方法で利用できるのかをまとめてきました。
しかし、具体的に就労継続支援B型作業所の利用を開始するまでの手順がわからない方もいるのではないでしょうか。
ここからは、就労継続支援B型作業所はどんな人が対象者なのかを確認して通所するまでの流れを紹介していきます。
下記のとおり、利用するまでの手順は大きく分けて6ステップあります。
- 自分が就労継続支援B型の対象者かどうか調べてみる【障害認定されていれば対象者】
- お問い合わせ(市町村役場/ハローワーク/障害者基幹相談支援センター/就労継続支援B型作業所)
- 日時を擦り合わせて利用希望先の作業所を見学する
- 利用前の手続き(障害福祉サービス受給者証の申請)
- 障害福祉サービス受給者証の発行
- 通所(利用開始)
障害福祉サービス受給者証が発行されるまでの期間には、個人差があります。
そのため、利用したい就労継続支援B型作業所が決まったら、早めに申請手続きを進めましょう。
また、初めて就労継続支援B型作業所を利用する場合は、障害福祉サービス受給者証に暫定期間として原則2か月間の有効期限が記載されます。
以降も継続して通所できそうだと判断された場合には、3か月間~1年間で有効期限が延長されますので安心してください。
就労継続支援B型作業所を利用するまでの流れは、下記の記事で詳しく解説しています。今すぐ通所したい方にとって大切な情報を掲載していますので、ぜひこちらもご確認ください。
自分に合った就労継続支援B型作業所の選び方は?どんな視点で見極める必要があるのか7つのポイントで解説!

就労継続支援B型作業所はどんな人が通うのか?どんな仕事をするのか?また、どんな障害の人が利用できるのか?理解できても、自分に合った作業所の選び方は難しいものです。
どんな視点で見極めていけばよいのか知りたい方は必見。ここでは、自分に合った就労継続支援B型作業所の選び方を、下記の7つのポイントで解説しています。
- 就労継続支援B型作業所内の雰囲気
- 無理なく通所し続けられる
- 自分の体調に合った頻度で利用ができるかどうか
- 就労継続支援B型作業所までの交通手段
- 自分のやりたい仕事内容がある
- もらえる工賃の金額
- 就労継続支援B型作業所を卒業した後の将来像がイメージできる
自分に合った就労継続支援B型作業所を無事に見つけることができれば、仕事をして金銭的(工賃)にも儲けたり、思いもよらぬ働き方で新しい自分を発見し結果として儲かる仕組みをつくりあげることもできるでしょう。
通所して自分自身の将来を見据えたときの希望がみえてくる作業所を選ぶことが重要です。
それでは、詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型作業所内の雰囲気
作業所により雰囲気はさまざまです。例えば食品を扱うことを中心にしている作業所は会話が少なかったり、逆に内職や手作り雑貨などを中心に扱っている作業所は和気あいあいと会話が飛び交っていたりと雰囲気は作業所によって違います。
その中で自分にあった作業所を見つけるためにもまずは見学、体験をしてみるのもいいでしょう。さらに言えば、利用している人数、男性、女性の比率なども視野にいれてみると決めるとき判断材料になるでしょう。
無理なく通所し続けられる
雰囲気の確認ができたら、無理なく通所し続けられるかの確認をしましょう。例えば、朝早くは薬の影響で難しいのでお昼からの利用希望、午前中のみ、午後のみなど自分にあった利用時間も通所し続けられる要因の1つです。自分の希望はしっかり伝え対策をしましょう。
さらに、場所の利便性や職員のスキルもみると通所し続けられるかの決めてになります。例えば、聴覚障害のある人の場合、職員に手話ができる人がいると安心して利用ができることでしょう。公共交通機関を利用して通所をしたいと希望の人は、駅やバス停が近いと無理なく通所がし続けられると思います。
自分の体調に合った頻度で利用ができるかどうか
就労継続支援B型は決められた利用日数はありません。例えば 週5〜6日の開所日のうち、自分が通える日数、時間で問題ないでしょう。 毎日通えるなら週5日の利用も可能ですし、体調にあわせて週1日以下での利用も可能です。
天候や気候によって体調に変化がある人もいることでしょう。その場合、無理して利用する必要はないので体調に合わせて利用出来るか確認することも重要です。
就労継続支援B型作業所までの交通手段
就労継続支援B型の事業所によっては自宅やグループホームから事業所までは送迎があるが、作業所が別の場所にある場合、作業所までの送迎がないことや距離の制限があるところ、訓練の為に公共交通機関を利用する場合も存在します。さらに車いすの送迎が困難と言われる場合もあるのでしっかり確認することをおすすめします。
反対に作業所が同じ敷地内、事業所と同一の場所など移動をしなくてもよい場合もあります。
作業所まで移動があるとき、不特定多数の人との移動が困難、自分で移動手段を確保したい、訓練の為に公共交通機関を利用したいなど希望がある人は、駐車場の有無、最寄りの
バス停、駅の場所、料金の支払い方法なども確認しておきましょう。
自分のやりたい仕事内容がある
就労継続支援B型には仕事内容にそれぞれ特徴があります。例えば、農業に特化している、PC作業が中心、手作り品の取り扱いなど多岐にわたります。自分のやりたい事、将来的にどんな職業につきたいかなどイメージし、やりたい仕事内容があるところをしっかり見極めましょう。
反対に自分にあった「仕事がない」という場合もあります。例えば、PC作業だと文字入力・文字おこし、動画制作、ブログ管理、など作業内容もさまざまです。作業所により作業内容にPC作業と明記されてても内容が細かく確認出来ないこともあるので、決めるときは自分のやりたい仕事内容が含まれているか、また、やりたい仕事内容を提供してもらえるかなど確認し「仕事がない」状況にならないようにしましょう。
もらえる工賃の金額
就労継続支援B型では、もらえる工賃の金額は規定がないので作業所によりさまざまです。全国平均工賃は月額で約15,000円ですが、利用頻度や仕事内容により上下するでしょう。そのため、どうすれば自分の目標とする工賃額になるか事業所と相談します。
その上で自分に可能な仕事内容であるか、自分が出来る仕事内容だとどのくらいの工賃がもらえ、工賃アップのために何が必要か何をすればいいかなどしっかりイメージしそのイメージに返答がある作業所を見つけましょう。
就労継続支援B型作業所を卒業した後の将来像がイメージできる
まず就労継続支援B型には利用期間の制限はありません。ですがスキルアップをし安定して作業が出来るようになると、A型への就労移行や一般就職など就労継続支援B型の卒業を視野にいれていくことでしょう。その時B型でどんな作業をしたかが自分の自信につながります。卒業後の将来像がイメージできるように準備していると仕事内容の幅が広がり、またどんな仕事がしたいのか、自分にあっているかなど漠然としていたイメージも明確にすることができるでしょう。
自分が卒業してどの道に進むかでもまた違ったイメージとなります。例えば、障害者雇用で一般就職した場合と個人事業主となり自分自身で仕事の獲得をしていく場合では全く違うイメージが必要です。どちらが自分に合っているか、またどちらになりたいかで身に着けるスキルや情報も変わるので将来像のイメージはとても大切といえます。
就労継続支援B型作業所は、あなたの人生において未来を切り開くための過程です。
仕事に対する意欲や自信がついたら卒業も視野に入れ、その後やりたい仕事を模索してみましょう。
就労継続支援B型作業所の卒業後におすすめの仕事(障害者向け)と選び方のポイントについては、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
【Q&A】就労継続支援B型はどんな人が通う?対象者は?

就労継続支援B型作業所はどんな人が通うのか、その対象者や利用条件などが理解できても、ふと疑問に思うことも出てくるでしょう。
ここでは、就労継続支援B型はどんな人が通うのか?というテーマで、下記によくある質問(Q&A)をまとめました。
- 就労継続支援B型作業所を辞めたくなったらどうしたらよいですか?
- 就労継続支援B型から一般就労する割合はどのくらいですか?
- 就労継続支援B型作業所だけ利用しても生活できないって本当ですか?
- 就労継続支援B型作業所は障害認定されていない健常者でも利用できますか?
それでは、詳しくみていきましょう。
Q1)就労継続支援B型作業所を辞めたくなったらどうしたらよいですか?
A1)基本的に手続きなどはないので、辞めたい意思を伝えればよいでしょう。
※就労継続支援B型は雇用契約がないので退職届や保険関係の手続きなど具体的になにかしないといけない事はありません。ですが、お互い円満に退所するため、社会へのステップアップのビジネスマナーとして退所したい1ヵ月前には日付けを明確にし意思を伝えておくとよいでしょう。その際理由も伝えるとさらによい関係性で退所ができます。
作業所によっては退所の際、ルールがある場合もあります。契約の時に確認するか辞めたい意思を伝えたときに確認しておくと安心です。
Q2)就労継続支援B型から一般就労する割合はどのくらいですか?
A2)厚生労働省が示している資料より令和元年で13.2%です。
その他にも、就労継続支援B型の利用者が年々増加傾向にあること、事業所が利用者獲得のためそれぞれに就労の専門性や特色が出てきたことも要因の1つです。
Q3)就労継続支援B型作業所だけ利用しても生活できないって本当ですか?
A3)就労継続支援B型だけでは生活できない可能性はあります。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばないので、最低賃金などの労働関連法規が適用されません。そのため、作業所によっては仕事内容により低単価の出来高払いが多いために工賃は低く、工賃だけで生活することは難しいでしょう。
ですが、作業所により利用者の持っているスキルに応じて時給制で工賃支払いを行っている場合もあります。工賃だけでの生活は難しくても、公的年金や生活保護費などを合わせると生活が可能になることもあるでしょう。
Q4)就労継続支援B型作業所は障害認定されていない健常者でも利用できますか?
A4)できません。
就労継続支援B型の利用者がどんな人か説明すると、身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている方。が対象と規定があります。ですが、障害者手帳が必ず必要というわけでもありません。
理由として、就労継続支援B型を利用出来る対象者はお住いの市区町村によっては、医師からの診断書や通院証明があれば就労継続支援B型制度を利用することは可能だからです。
またどうしても就労継続支援B型の利用がしたい健常者の人は職員としての利用なら可能かもしれません。
まとめ|就労継続支援B型は幅広い年齢層と障害を持った人が自分のペースで利用できる場所!

今回は、就労継続支援B型作業所はどんな人が通うのか?具体的な対象者や利用条件、年齢制限などについて解説してきました。また、精神障害者や知的障害者、身体障害者などの特徴や利用に際しかかる費用・仕事内容・工賃受給までの手順なども紹介しました。
就労継続支援B型は、何も障害を抱えていない健常者が通所することはできない仕組みですが、興味があれば職員(職業指導員/生活支援員など)での就職やボランティアでの参加を検討するのもよいでしょう。
最後に、本記事の内容を下記にまとめました。
- 就労継続支援B型作業所は「精神障害」「知的障害」「身体障害」「発達障害」「難病」の障害を抱えた人が通う
- 原則18歳以上の成人で障害認定を受けている人であり、障害福祉サービス受給者証の発行を受けている人が就労継続支援B型作業所を利用できる
- 就労継続支援B型作業所の利用料金は0円~37,200円で、前年度所得に応じて変動する
- 就労継続支援B型は、作業所内外で仕事(作業)をした対価として工賃をもらう
- 工賃金額や作業所の雰囲気、やりがいなどを見極めて自分に合った選び方をすることが重要
- 就労継続支援B型作業所の利用を辞めたいときは、管理者(職員)に相談するだけで簡単に辞められる
- 健常者は、就労継続支援B型作業所に利用者として通所できない
どんな人が就労継続支援B型作業所の利用対象者なのか?というテーマでまとめてきましたが、最後まで読み進めたあなたは「どんな障害の人が通うのか」「どんな仕事をしているのか」深く理解できたことでしょう。
就労継続支援B型作業所の利用料金や自己負担金の仕組み、厚生労働省の公式見解については、下記の記事で詳しく解説しています。
就労継続支援B型作業所に興味のある方にとって絶対に必要な情報をまとめておりますので、ぜひご覧ください。
「もしかしたら、就労継続支援B型作業所を利用できる対象者かも?」と思った方、もしくは就労継続支援B型作業所「ワークショップOHANA」が気になった方は、ぜひ下記のボタンからお問い合わせください。
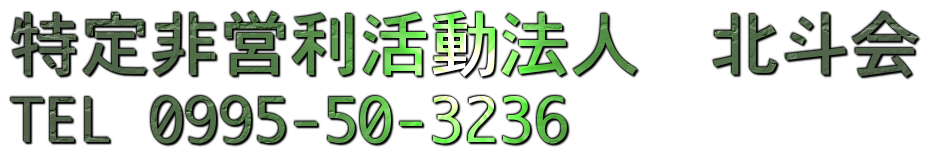
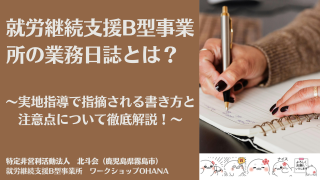
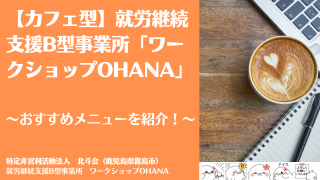
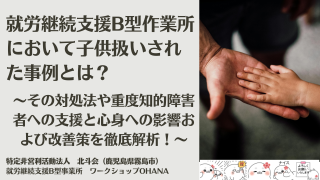

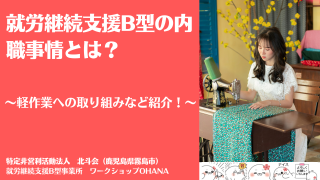
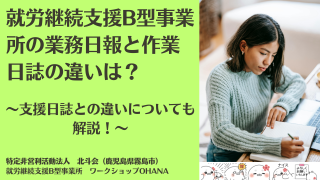
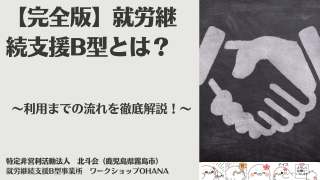
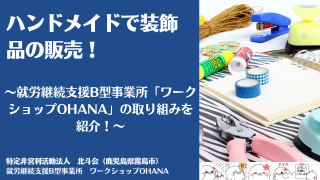
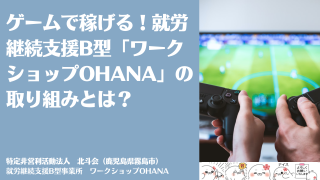
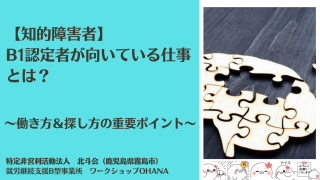
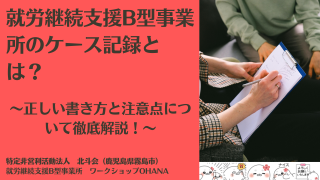
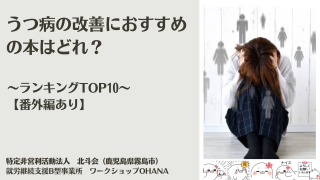

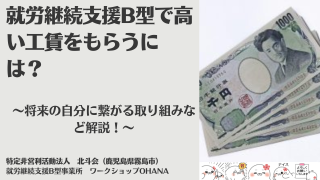
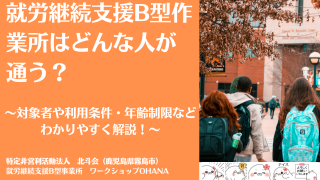
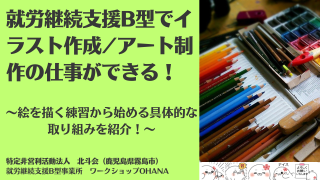
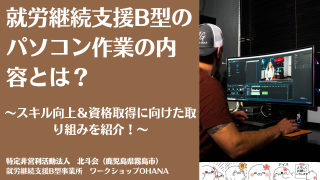
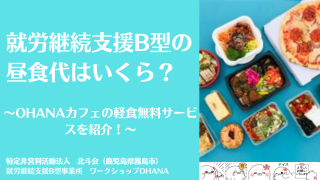

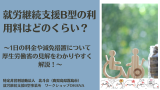

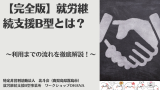



コメント